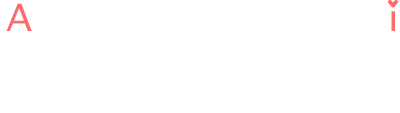障害者福祉サービス
- [公開日:2024年10月22日]
- [更新日:2024年10月22日]
- ID:1859
制度について
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、介護給付(日常生活の支援等)、訓練等給付(生活訓練、就労に向けての支援)に分けられます。
サービスは、障がいの状況(障がいの程度や社会生活状況、介護者の状況等)を勘案し、いろいろなサービスを組み合わせて利用することができます。
また、障がい者が地域生活を円滑におくるため、状況に応じて柔軟に対応できる「地域生活支援事業」も実施しています。
| サービス名 | サービス内容 |
|---|---|---|
介 | 居宅介護 | ホームヘルパーが訪問し、身体介護や家事援助、通院の付き添い等をおこなう。 |
(身体介護) | 食事・入浴・排せつのお世話、衣類やシーツの交換等 | |
(家事援助) | 掃除・洗濯・買い物・食事の準備等 | |
重度訪問介護 | 常時介護を要する重度の肢体不自由者(児)に、居宅においての入浴・排せつ・食事の介護・乗降介助・家事援助・見守り・外出時の移動中の介護等を総合的におこなう。 | |
同行援護 | 移動に著しい困難を有する視覚障がい者(児)等の外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の支援等をおこなう。 | |
行動援護 | 常時介護を要する知的または精神障がい者(児)が行動上著しい困難を伴う場合、その危険を回避するための援護、外出中の介護等をおこなう。 | |
短期入所 | 在宅で生活をされている障がい者(児)を介護している方が、疾病やその他の理由により、介護が困難になった場合等に短期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護等をおこなう。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的におこなう。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を要する障がい者(児)に、主に日中において、病院その他の機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話をおこなう。 | |
生活介護 | 常時介護を要する障がい者(児)常に、日帰りで、入浴、排せつ、食事等の介護サービスや、創作活動等の支援をおこなう。 | |
施設入所支援 | 施設への入所が必要な障がい者(児)に夜間や休日における食事・排せつ・入浴の介助等の支援をおこなう。日中においては、生活介護サービスを組み合わせて利用できる。 | |
訓 | 自立訓練 | 障がい者が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために、必要な訓練やその他の援助をおこなう。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間、生産活動その他の活動の機会を提供して、就労に必要な知識・能力の向上のための必要な訓練その他の援助をおこなう。 | |
就労継続支援A型 | 雇用契約に基づいて就労が可能と思われる障がい者に働く場を提供し、就労に向けての支援をおこなう。 | |
就労継続支援B型 | 一般企業等での就労が難しい障がい者に、働く場を提供するとともに、就労に向けて必要な訓練やその他の援助をおこなう。 | |
就労定着支援 | 一般企業等に新たに雇用された人の就労継続を図るため、関係機関との連絡調整や、日常生活・社会生活を営む上での相談、指導、助言等の支援をおこなう。 | |
共同生活援助 | 夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活の支援を行う。日中に、就労・自立訓練・就労移行支援等を受けていて、共同生活を営むのに支障のない知的・精神障がい者が対象 |
サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など |
医療型児童発達支援 | 上肢または下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援および治療 |
放課後等デイサービス | 授業の終了後または休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行う |
保育所等訪問支援 | 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う |
サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
日常生活用具の給付 | 日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的として、重度障がい者に対し、自立支援用具等の日常生活用具の給付等をおこなう |
移動支援 | 地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とし、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援をおこなう |
日中一時支援 | 障がい者等の家族の就労支援および障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、障がい者等を一時的に預かり、日中における活動を確保する |
訪問入浴 | 身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とし、訪問により居宅において入浴サービスの提供をおこなう |
意思疎通支援 | 聴覚、音声言語機能障がい者(児)の社会生活の利便性の向上を目的とし、手話通訳および要約筆記をおこなう者を派遣し、意思疎通の円滑化を図る |
地域活動支援センター事業 | 障がい者等の地域生活の促進を図ることを目的とし、地域の実情に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を便宜を供与する地域活動支援センターの機能を強化する |
相談支援 | 障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的に、障がい者(児)の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助をおこなう |
サービス利用申請について
サービスを申請するには
身体・療育・精神の障がいをお持ちの方は、役場福祉課にて申請受け付けをします。障がいをお持ちの方の福祉サービスの必要性を総合的に判断するために、支給決定の各段階において、
障がい者の心身の状況(障害支援区分)
社会活動や介護者、居住等の状況
サービスの利用意向、利用計画
訓練・就労に関する評価を把握
以上の要素を勘案したうえで、支給決定をおこないます。
新規に申請する場合
受けたいサービスを担当者にご相談ください。状況により、生活状況等を詳しくお聞きすることもあります。
【お持ちいただくもの】
・各種障害者手帳等
・所得課税証明書または非課税証明書(転入者のみ)
・個人番号カードまたは通知カード
※市町村民税非課税世帯で、障害年金等非課税年金受給者については、年金振込通知書または証書等(年金や手当の額がわかるもの。写しでも可)をお持ちください。
支給量の変更を申請する場合
変更したい、または追加利用したいサービスを担当者にご相談ください。
【お持ちいただくもの】
・各種障害者手帳等
・各種受給者証
・個人番号カードまたは通知カード
支給決定までの流れ
【介護給付を希望する場合】
(1)相談
福祉課または相談支援事業者に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。
(2)利用申請
窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。
(3)調査(アセスメント)
障がいの状況等について、全国統一の調査項目にしたがって調査をおこないます。
(4)調査・認定
調査の結果をもとにコンピュータで一次判定を行います。その後、審査会において一次判定資料、医師意見書等をもとに障害支援区分認定をおこないます。
(5)サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。
(6)支給決定
サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定をおこないます。支給決定内容を、支給決定通知書および受給者証に記載し、交付します。
支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。その後、サービスの利用が可能となります。
【訓練等給付を希望する場合】
(1)相談
福祉課または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。
(2)利用申請
窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。
(3)調査(アセスメント)
障がいの状況等について、全国統一の調査項目にしたがって調査をおこないます。
(4)サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。
(5)支給決定
サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定をおこないます。支給決定内容を、支給決定通知書および受給者証に記載し、交付します。
支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。その後、サービスの利用が可能となります。
【障がい児通所支援事業を希望する場合】
(1)相談
福祉課または相談支援事業者に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。
(2)利用申請
窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。
(3)調査(アセスメント)
児童の状況について、全国統一の調査項目(5領域11項目等)にしたがって調査を実施します。
(4)サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。
(5)支給決定
サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定をおこないます。支給決定内容を、支給決定通知書および受給者証に記載し、交付します。
支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。その後、サービスの利用が可能となります。
利用者負担について
利用者負担は、原則として費用の1割です。
利用者負担の軽減措置として、以下の負担上限額が設定されています。
区分 | 負担上限月額 | 要件 |
|---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
一般1 | 9,300円 | 市町村民税課税世帯 |
一般2 | 37,200円 | 上記以外 |
所得を判断する際の世帯範囲
※障がい者(施設入所の18,19歳を除く):本人とその配偶者
※障がい児(施設入所の18,19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!